🟦 ① はじめに:どこからが副業か”が問題になるのか

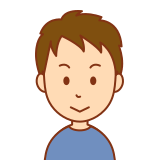
副業としてブログをやってみたいな
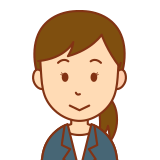
動画を投稿して収益化できたけど少しだったからいいかな
副業をしている人の中にはそう思っている人もいます。副業可能な会社員であれば問題ありませんが、公務員という立場で副業で稼いでいることがおおやけになると、問題が大きくなります。
その問題には地方公務員法第38条「営利企業従事の禁止」が関係しています。副業と判断されてしまうと、懲戒処分になる可能性がありますので、ご注意ください。
この記事を読めば、どこまでが副業で、どこまでがセーフなのかがわかります。
🟦 ② 副業の定義:法律上の「副業」とは

副業という言葉、今ではよく使われていますよね。でもその言葉が何を意味するのかは意外と知らないことが多いです。
法律上 ”副業”という言葉は明確に定義されていません。民間企業の場合は厚生労働省が2018年に「副業・兼業に関するガイドライン」を公表しています。
副業・兼業とは
(厚生労働省「副業・兼業の促進に関数ガイドライン」)
本業(主たる職業)を持つ労働者が、
それ以外の仕事に従事し、収入を得ること。
民間企業では、「報酬を得てほかの仕事をすること」が副業とされています。
公務員(教員)の場合は、地方公務員法で副業に関する基準が示されています。
職員は、任命権者の許可を受けなければ、
(地方公務員法第38条)
自ら営利企業を営み、または他人の営利企業の役員・従業員等となってはならない。
公務員の場合は、「報酬を得て継続的に行う業務」は原則”副業”と定義されます。自分で会社を立ち上げて起業することや、ほかの企業に雇われて報酬を得ることは原則禁止です。
営利企業とは、株式会社や個人事業主など報酬のある活動全てが対象。公務員として副業をしていくためには、教育委員会など任命権者の許可が必要になります。
📌 まとめ表:
| 行為 | 報酬あり | 継続的 | 副業扱い? |
|---|---|---|---|
| ブログで広告収入 | ○ | ○ | 副業 |
| 一度だけ講演して謝礼をもらう | ○ | × | グレー(内容次第) |
| 教育ボランティア | × | ○ | 副業ではない |
| 家族の農業を手伝う(無償) | × | ○ | 副業ではない |
🟦 ③ 「収益があるか」が最大の判断基準

副業の判断基準は「金銭的な報酬があるかどうか」が一番のポイントです。ブログやyoutubeでの広告収入や書籍の原稿料、全てが「収益」とみなされます。
振込先の銀行を変えたり、ポイント還元にしても同様で、形を変えても収入になる可能性があります。
🗒️ 補足:
「収益が発生した瞬間に副業とみなされる」わけではないが、
“営利目的で行っている”と判断されると副業に該当する。
🟦 ④ 「目的」と「影響」も判断基準になる

収益を受け取っているかだけが副業の判断基準ではありません。公務員としての規定にしたがっているかにも細心の注意を払う必要があります。
営利目的でなくても「職務に支障がある」「信用を損なう」場合はNGです。SNSで生徒や勤務先の情報を発信することは控えましょう。収益が発生していなくても、同様です。
公務員として信用失墜行為はダメですよ。取り返しがつかないですから。
| 規定 | 禁止される理由 | 具体例 |
| 地方公務員法第33条 | 信用失墜行為の防止 | 勤務先や生徒のことについてSNSで発信する |
| 地方公務員法第38条 | 営利活動の禁止 | 企業の案件などで報酬を得る |
| 教育公務員特例法第9条 | 教育の中立性の保持 | 政治・宗教・企業を特定して推奨する発言や行為 |
📌 チェックリスト:
- 本務に支障がないか
- 学校や生徒に悪影響がないか
- 教員の立場を利用していないか
🟦 ⑤ グレーゾーン事例を整理してみよう

実際に副業として許可されるケースとそうでないケースを比べてみましょう。
| 活動内容 | 副業になる? | 理由 |
|---|---|---|
| 趣味ブログ(広告なし) | ❌ | 収益目的でない |
| YouTubeで教育系動画を投稿(収益あり) | ⭕ | 広告収入が発生 |
| 教育講演を一度だけ実施(謝礼あり) | △ | 内容・頻度次第 |
| 自作教材を販売 | ⭕ | 営利目的の取引 |
| 地域のスポーツクラブで指導(無償) | ❌ | 社会貢献活動 |
ブログやyoutubeであっても収益化されていたり広告が貼られていると副業とみなされます。反対に、収益目的ではない発信であれば問題ありません。
副業として認識されるかどうかは、「報酬(収益)が発生しているか」「継続的か」を見て判断されます。講演会やセミナーで一度だけ報酬を受けていた場合はグレーゾーンになるわけです。
しかしながら、副業としてみなされてしまうと後々面倒なので、早いうちに上司や管理職に相談しておくことをオススメします。
🟦 ⑥ 「副業かも?」と思ったらどうする?
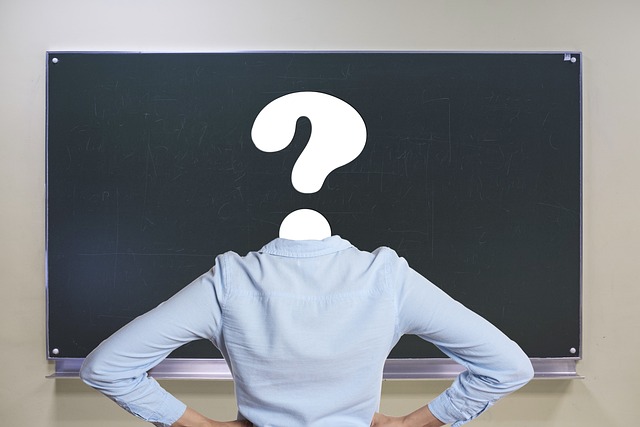
まずは上司や管理職に相談しましょう。信頼できる同僚であれば問題はありませんが、あまりオススメしません。もし副業を考えているという情報が出回ったときに関係が悪化してしまう可能性がありますし、情報はどこから漏れるかわからないので、同僚に相談するのはそれなりのリスクがあります。
副業を認めるのは、自分が所属している組織の長です。教員でいうと「教育長」です。地方公務員法には以下のように示されています。
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業などの業務に従事してはならない。
地方公務員法第38条
つまり、副業の許可は任命権者(=その職員を採用・任命する権限を持つ人)が出します。
⚠️注意点としては、いきなり教育長に連絡するのはやめましょう。
副業の許可を得るためには正しい手順を踏まなければいけません。
①「副業許可申請書」を作成し、校長へ提出する
②校長が内容を確認し、教育委員会へ上申する
③教育委員会事務局が審査
④教育長(任命権者)が許可・不許可を決定
大事なのは、事後報告ではなく、事前報告が必要ということです。収益を得てから報告すると懲戒処分になってしまう可能性も十分あり得ますので、誠実に丁寧に報告するようにしましょう。
🟦 ⑦ まとめ:副業の基本は“収益・目的・影響”の3点で判断

今回の記事で知っていて欲しいのは、副業全てが懲戒処分になってしまうということではなく、適切に法令遵守をして、正しい手順で副業をしましょうということです。
基本的には、収益を得ることで副業とみなされてしまいます。収益がなくても、法律を守れていないと副業扱いになってしまうケースもありますので、ご注意ください⚠️
とにかく、不安を感じたときは学校長や教育委員会に相談することが安全です。教員の場合、副業許可申請書を一番最初に見るのは学校長になりますので、同僚などではなく、学校長に直接確認、相談できるといいと思います。
何も知らずに副業あつかいをされて懲戒処分になるのは、不本意ですので自分でもよく調べて、安全にスキルアップしていきましょう。
💡 一言まとめ:
「やっていいか迷ったら“収益・目的・影響”の3つで考える」
→ セーフかアウトかの判断が明確になる


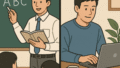
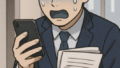
コメント