 未分類
未分類 小さい頃の習い事は「未来への投資」人気のある習い事5選!
小さい頃からの習い事、何を選ぶべき?「子どもには何か習い事をさせたほうがいいのかな?」「小さい頃から始めるなら、どんな習...
 未分類
未分類  生活
生活  未分類
未分類 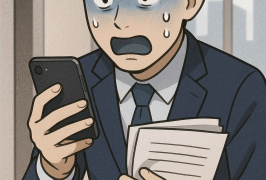 未分類
未分類  未分類
未分類 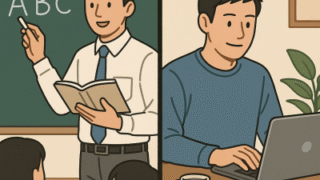 未分類
未分類 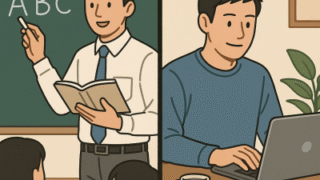 未分類
未分類 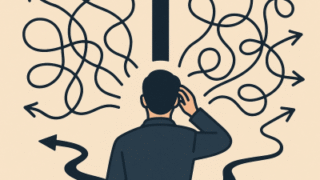 本
本 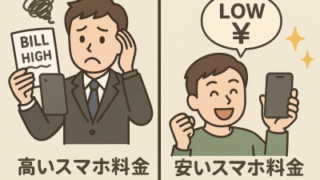 勉強
勉強  生活
生活