1. はじめに
「非認知能力」という言葉を聞いたことはありますか?
近年、
実はこの「非認知能力」、学校のテストでは測れないけれど、
本記事では、非認知能力と認知能力の違いを分かりやすく解説し、
⸻
2. 非認知能力とは?
非認知能力とは、数値化しにくい力のこと。
非認知能力は「テストや学力で測れない力」
代表的な非認知能力には以下のようなものがあります。
- 自己制御力:感情をコントロールし、目標に向かって行動する力
- やり抜く力(グリット):諦めずに挑戦を続ける力
- 協調性:他者と協力し、共感する力
- 自己肯定感:自分に自信を持ち、失敗しても立ち直れる力
- 好奇心・探究心:新しいことに挑戦したい気持ち
OECD(経済協力開発機構)の調査でも、
⸻
3. 認知能力との違い
では、認知能力とは何でしょうか。
・認知能力:読み書き・計算・記憶力など、テストで測れる力
・非認知能力:忍耐力や協調性など、テストでは測れない力
両者の違いを一言で言えば、
 「認知能力=知識やスキル」「非認知能力=人間性や態度」
「認知能力=知識やスキル」「非認知能力=人間性や態度」
どちらか一方だけを伸ばしても不十分で、
認知能力はその実力を測ることも容易にでき、力を伸ばすことは
⸻
4. 非認知能力と認知能力の相乗効果
非認知能力と認知能力は、それぞれ単独で存在するものではなく、
- やり抜く力 × 読解力 → 難しい文章でも最後まで読み切れる
- 自己肯定感 × 数学力 → 苦手な問題にも挑戦できる
- 協調性 × 知識 → グループで学ぶときに力を発揮できる
つまり、認知能力を活かすためには非認知能力が必要であり、
⸻
5.非認知能力を育てる具体的な方法
家庭でできること
遊びや体験(外遊び、キャンプ、工作など)
手や体を使ってする動きを取り入れることで、学力では測ることができない力が身につきます。
また、家庭の中だけじゃなく、外の世界のことを知ることができるので、子どもの経験って案外大切です。
キャンプなどは準備に時間とお金がかかってきますので、楽しくできたり余裕があればぜひチャレンジしてみてください。
もしその余裕がなくても、無料で開催されているイベントや教室に参加できれば、それだけでも子どもの経験が積み重なっていくので安心してください。
結果ではなく「努力・過程」をほめる
社会に出て仕事をしていると、やっぱり過程より結果が重視されていきます。
親として仕事と育児を両立させている人にとっては当たり前ですよね。
結果を誉めることで子どものモチベーションが上がることは間違いないのですが、より効果を出していくためには、「ここまで頑張れたのがすごいよ!!」と過程をしっかり褒めてあげましょう。
失敗してもすぐに助けず、自分で考える時間を与える
「失敗」と聞くと
『子どもには失敗を経験してほしくないな』
『失敗は少ない方がいいよね』
って思う人もいるんですが、失敗をして学ぶことも世の中にたくさんあるってみんなが知っていることですよね。
「失敗させる」じゃなくて『失敗しても再挑戦できるように環境を整えてあげる』っていう考えが大切です。
学校・習い事でできること
- スポーツ:協調性・忍耐力を育む
- 音楽や演劇:表現力や創造性を育む
- プログラミング:論理的思考力+やり抜く力を鍛える
 ポイントは「勉強以外の場でも育まれる」ということ。
ポイントは「勉強以外の場でも育まれる」ということ。
⸻
6. 相乗効果を最大化するおすすめ教材・習い事
では、実際にどんなサービスや教材が「認知能力+非認知能力」
ここでは実際に人気のあるものをご紹介します。
- 通信教育
- スマイルゼミ :学習習慣とやり抜く力を育てられる
- 進研ゼミ :基礎学力+挑戦する気持ちをサポート
- Z会:思考力・探究心を育てたい家庭におすすめ
- 知育玩具サブスク
- トイサプ :遊びながら非認知能力を伸ばす
- オンライン英会話 :コミュニケーション能力+英語力
- プログラミング教室 :論理的思考+粘り強さ
⸻
7. まとめ
非認知能力は、テストでは測れないけれど、
認知能力とセットで育てることで、
家庭でも学校でも、今日からできる小さな工夫があります。
「子どもの未来を広げる力」を、

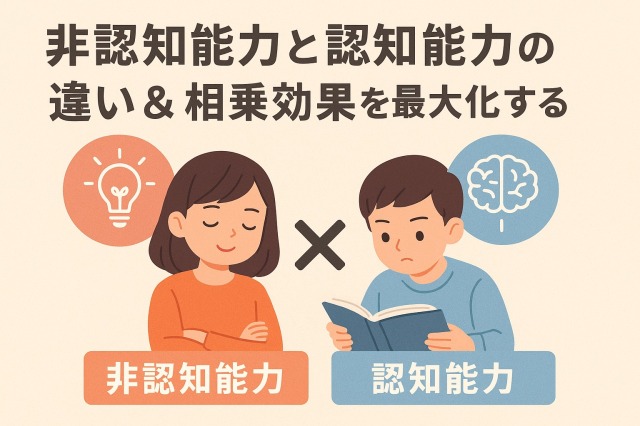


コメント