子どもがウソをついたことがわかったとき、みなさんならどうしますか?
大人でも子どもでも都合が悪くなったりすると、ウソでその場を乗り切ろうとしますよね。
親として、そのことがわかっていても気づいたときには悲しみや驚きが大きいかもしれません。
しかし、ウソは子どもの成長の一環であり、心理的な理由が背景にあるかもしれないということをしっておくと怒らずに済むかもしれません。怒ると、子どもはより巧妙にウソをつくようになったり、怒られないようにウソを重ねて上手く回避したりするようになります。
この記事では、子どもがウソをついているときにどんな行動をするのか、子どものウソを見抜くポイントや怒らずに正しい方向へ導く方法をお伝えします。参考になれば幸いです。
1,子どもがウソをつく理由
なぜ、子どもはウソをつくのでしょうか。
それは、大きくは『自分を守るため』です。
とくに、小学校くらいの年齢になってくると自分だけの世界だけでなく、友だちとの関係や兄弟、家族と自分の世界が共有できるようになってきます。
「周りに認められたい」「ガッカリされたくない」など理由はさまざまですが、子どもなりにウソをつくのは自分の心や気持ちを守るためでもあるのです。
自分が正しいと思うことをできているのであれば、ウソをつく必要はありませんので、何かべつの気持ちがあるのだと考えられます。
子どもがウソをつくののは心理的な原因もあり、『褒められたい』『叱られたくない』という気持ちの表れです。
ただし、そんな子どものウソに気づいたときに親がどんな行動をとるのかを子どもはよく見ています。
だからこそ、伝え方がとても重要になってくるのです。
率直に「ウソはダメ」と言うだけでは子どもにも伝わりにくいです。
基本は、子どもがどんな心理状態なのかを理解しようとすることです。何もわからないまま、自分の感情をぶつけるだけでは、子どもとの関係も険悪になっていき悪循環になるのだけは避けましょう。
子どもの背景を理解して、どんな言い方がいいのかも一緒に考えていきましょうね。
2,子どものウソを見抜くポイント
まず重要なとこは、子どもの言葉と仕草をよく観察することです。
子どものことを信用することは重要ですが、子どもの言っていることを鵜呑みにするのだけは、とくに気を付けてくださいね。疑うんじゃなくて、いろんな視点から見ようってことです。
子どものウソを見抜くポイント以下の3つです。
- 行動の矛盾があるかどうか
- 表情や仕草
- 詳細を言えるかどうか
①行動の矛盾があるかどうか
②表情や仕草
人がウソをつくときには、体のどこかに動きがあります。個人差はありますが・・・。
それは子どもも同じで、ウソをついているときには表情や仕草をよく見ておくようにしましょう。
例えば、話すときに目を合わせない、合わせてもすぐに違うほうへ目をそらす、など視線が頻繁に動いていれば、どこかにウソが隠れている可能性がありそうです。
他にも声のトーンが急にかわったり、落ち着きがなくなったりするので、どんな表情をしていて、体のどこの部分が動いているのかをよく観察しておきましょう。
『目は口ほどに物を言う』という言葉があるように、子どもの目の動き一つをとってもウソをついている可能性がありそうだと判断することができそうです。
③詳細を確認する
何か起こった出来事を子どもに聞くときには質問をしますよね。
ウソをついていると、その質問をした際、話や表現が曖昧だったり、矛盾が生じることがあります。
もちろんすべてを疑って、尋問のように話を聞いていくのではありません。
一つずつ、絡まったひもをほどくようなイメージをして話を聞いてあげましょう。
あまりしつこく聞いてしまうと、自分が何か良くないことをしたのではないか…と、たんに不安を与えることにもなりかねませんので、聞く度合いについては注意が必要です。
3,子どもを怒らずに導くには
まずは、子どもの気持ちを受け止めることです。
「ダメ!」と怒るのではなくて、「どうしてそう言おうと思ったの?」など、子どもの気持ちを理解しようとする姿勢が大切です。
ときには厳しく叱ることも大事だとは思いますが、そればかりだと、子どもの思ったことや感じたことを親に伝えることを躊躇してしまうようになります。
子どもの気持ちを聞こうと思ったら、まずは「あなたを傷つけるつもりはないんだよ」と安心させてあげることが大切になってきます。
ウソを責めるのではなく、正直に言うことの正しさと、それに伴うメリットについて話してみてもいかもしれませんね。
「正直に話してくれてありがとう」など、正直に言えたときに『正直に言っておいてよかった』と思えるように関わっていきましょう。
子ども自身が正直にいられる環境をつくっていくのが大切です。
子どもがウソをつく原因に「怒られる恐さ」があります。子どもが怒られるくらいならウソをついてその場をやりすごそう、と思ってしまう前に、怒るのではなくその代わりに問題を一緒に解決していく姿勢を示していきましょう。
子どもが『正直でいたほうが居心地がいい』と思えるようになると、子どもにとって正直にいることができる環境だといいですよね。
そのときに重要になってくるのが『親も、子どもに対して正直にいる』ことです。
仮にウソをつくような形になってしまったとしても、親だからとうやむやにするのではなく、謝ることや正直なことを伝える姿勢を見せてあげましょう。
4,まとめ
どうでしたか?子どものウソをただ叱るのではなく、その背景にある気持ちや考えていることを理解しながら対応することが重要です。
相手を傷つけたり悲しい思いにさせるウソに関しては、個人的にきつく叱るべきだと思いますが…。
そうだとしても、ウソをつくこと自体、自分のためにならないということをきちんと伝えていきましょう。
そうはいっても、根底にあるのは親子の信頼関係です。
子どもとの信頼関係を深めるような対応を心がけて、親も子どもも正直でいられる環境を整えていきましょう。
質問やエピソードがあれば、コメント欄で教えてくださいね。


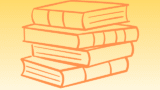
コメント