はじめに:目を併せて話すことは重要?
子どもと関わっていく中で、「子どもと話をするときは、目を併せて叱り伝えましょう」と言われることってありませんか。
大事な話のときや真剣な話をするときにはとても有効だとは思いますが、結論を言うと『ほどよく目を合わせに行き過ぎる』のは避けたほうがいいということです。
子どもと目を合わせると自分の気持ちを伝えやすい反面、意図せず威圧を与えることになってしまい、子どもも目をそらしたり、話半分に返事をしたりする可能性があります。
小学生の子どもも自分の考えや世界観を持っていますから、その世界を守りたいと思っています。
しかも、自分の思っていることを100%伝えるのは大人でも難しいですし、子どもならなおさらです。それほどの語彙力もまだまだ未熟ですしね。
この記事では、あえて「目線」を子どもから外すという新しいアプローチで子どもとよりよい関係を築いていく方法を一緒に考えていきましょう。
1、目線を合わせる落とし穴
子どもと目を合わせてとき、その子はどんな反応を見せますか?
じっと目を合わることができる子もいれば、ふらふらしたり、目をそらしたりするこも必ずいるはずです。
そんななかで、無理やり目を合わせにいってしまうと、子どももプレッシャーを感じてしまい、ウソをついたり、黙り込んだりと大人が聞きたい答えから遠ざかってしまいます。
ある程度のプレッシャーは必要だと思いますが、過度になってしまうと逆効果になります。
また、こどもが言葉や表情で表現していても、態度や立ち振るまいからわかることもありますので、目を見るだけでは不十分だと考えられます。
仮に話をしているときに子どもがフラフラするのにも、その子なりの理由や気持ちが表れているのかもしれません。
子ども自身はそんなつもりはないのかもしれませんが、子どもに過度にプレッシャーを感じないほうが話し合いもスムーズに進むことが多くなりますよ。
さらに、大人から目線を合わせにいくと、大人のペースで話し合いが進み、子どもの話すタイミングなくなりかねないので、そこはぐっと我慢してあげましょう。
目線を合わせないことのメリット3選
メリット1:子どもの自然な行動をみることができる
子どもは、話している言葉以外でも、行動に気持ちが表れることが多いです。
目を合わせず、視界のはしっこで「どんなことをしてるのかな」とみてみるのもおもしろいですよ。
子どもをじっと見つめていると「監視されている?」と緊張が走って、自然体の姿を出しづらくなりますので。自然体の子どもの姿を見れたほうが、大人としてもほほえましいですよね。
そういった子どもがプレッシャーを感じていない状態のほうが、その子がどんなことを考えているのかがわかりやすくなります。
自然な子どもの行動を見れたほうが大人としても安心できますし、子どもたちも自然な姿を見せれたほうが気楽に生活が送れますので、お互いにメリットがあります。
メリット2:リラックスした会話ができる
心理学的にも、カウンセリングなどで誰かと話すときは、対面でよりもななめの角度で話を聞くのがいいと言われています。対面で話をすると受け手側が攻撃的にとらえやすいそうです。
子どもと話すときはカウンセリングではありませんから、横並びや背中あわせで話すとよいかもしれません。
適度に目線を外しつつ、子どももリラックスして話をしやすくなります。
テレビを見ながらとか、一緒に歩いているときとか、玄関から駐車場に行く途中でとか、短い時間でも十分です。
大事なことは、あえて視線を外しながら会話し、リラックスしている子どもの姿を引き出すことです。何気なく話せるような環境をつくれるようにしていきましょう。
メリット3:子どもが主体的に話せるようになる
子どもに何か伝えたいことがあると、すぐにでも教えてあげたくなるものですが、そこをぐっと我慢してみてください。緊急なものは別ですが。
目を合わせずに待つことで、子どももプレッシャーを感じることなく、自分の考えを言うことができるようになるかもしれません。
子どもが自分で話したいことを「選択」できる余地をのこしてあげましょう。
主体的に話すことで、自分で行動を選ぶことができますし、周りの状況にも流されにくくなります。
『たかが視線くらい・・・』と思われるかもしれませんが、子どもが話すことと大人が子どもに言わせるのとでは、主体性を育むのに大きくかかわってきます。
具体的なアプローチ方法:積極的なアプローチはしない
では具体的にどんなアプローチがいいのでしょうか。
3つ紹介します。
1⃣会話の場所を選ぶ
どんな場所でも話すことは同じと思いがちですが、周りに人がいるかいないか、自分になじみのある場所か、など、話をする場所でも子どもの心に影響を与えます。
話をするときに、周りの人から見られている状態で話す気持ちにはなれませんよね。しかも、自分の自然体を出そうとするのならなおさらです。
子どもが自分から話しても大丈夫かな。と思える環境を整えてあげましょう。
場所がかわるだけでも、想像以上にリラックスして会話ができるかもしれませんよ。
また、子どもは発する言葉だけではなくて、仕草や表情からでも感情や気持ちを表すので、それを表に出すことができるような場所選びを大人が意識的にしてあげましょう。
ポイントは「気楽に、何気なく」です。
2⃣質問のしかたをかえる
3⃣コントロールしようとしない
誰だって、他の人に話や行動をコントロールされていると感じると気持ちよくはなりませんよね。
それは子どもも同じで、自分のしたいことを制限されていると感情的になったり、本当のことを言えなかったりします。
なので、目を合わせて「何か言わなければならない」と感じさせるよりも、自分が話したいと思ったことを話せるようか関わりが大事なのです。
目線を合わせないことで、空間的な自由を感じることができ、自然な子どもの姿を見ることができるようになります。
そもそも、「子どもはコントロールできない」と心のどこかで思っておくことが、子どもと関わるうえで大切な考え方になってきます。
子どもの好き勝手にさせるのではありませんが、あくまでも大人ができるのは、口で伝えたり、自分の姿を見せることしかできないのです。
そのことを分かっているかどうかが今後の子どもとの関わりに大きく影響してきますよ。
まとめ
どうでしたか?
自分がふだん、子どもとどんなふうに関わってきたのか考えるきっかけになればうれしいです。
今回は”あえて”目線を合わせないことをテーマにしてきましたが、大事なことは固執しないことです。
目を合わせるにしても合わせないにしても、そのことに固執してしまうと自分も子どももしんどい気持ちになってきますからね。
視線よりも、子どもの行動や仕草、空気感に目を向けて、より豊かなコミュニケーションを目指していきましょう。


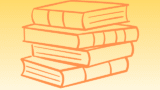

コメント