はじめに
学校で必ず使われている「学習指導要領」。
名前は聞いたことがあっても、
学習指導要領とは?
学習指導要領とは、
学校で教える内容や各教科の目標が示されており、
その目的は、
現行の学習指導要領では、次の3つの柱が重視されています。
- 社会に開かれた教育課程
- 主体的・対話的で深い学び
- カリキュラム・マネジメント
また、各教科の内容は
- 知識・技能
- 思考力・判断力・表現力
- 学びに向かう力・人間性
の3つに整理されており、
どの教科の学習するうえでも必要な基準になってきます。
学習指導要領はいつからある?
学習指導要領は、戦後の1947年(昭和22年)に「
その後、1958年(昭和33年)
現在の学習指導要領は本屋などでも販売されているので、簡単に手に入れることができます
日本だけの仕組み?
「学習指導要領」という名称は日本独自のものですが、
- アメリカ・カナダ:州ごとに「教育スタンダード」を策定。
全国共通の基準はなし。 - オーストラリア:「オーストラリアン・カリキュラム」を採用。
7つの能力と8つの学習領域を組み合わせ、 授業例や教材情報も充実。
つまり、日本だけでなく世界中の国々が、
どんなことが書かれているの?
学習指導要領は、「何年生でどんな勉強をするか」
国語・算数・理科・社会だけでなく、体育・音楽・図工・
重視されているのは、単なる知識の習得だけではありません。
- 考える力
- 判断する力
- 自分の考えを表現する力
- 他者と協力する力
こうした力を養い、
なぜ大事なのか?
学習指導要領は、
地域差や学校差に関係なく、
つまり、子どもたちが社会の変化に対応できるようにするための“
改訂はどのくらいの頻度?
およそ10年ごとに改訂が行われています。
例えば、情報化社会の進展を受けて「プログラミング教育」
まとめ
学習指導要領は、
- 1947年に始まり、約10年ごとに改訂されている
- 日本だけでなく世界各国にも教育課程がある
- 知識だけでなく「考える力」「表現する力」「協力する力」
も重視されている - 社会の変化に合わせて常にアップデートされている
普段はあまり意識することがないかもしれませんが、

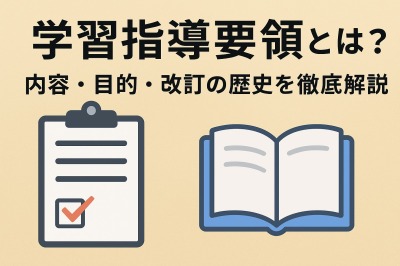
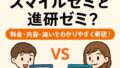

コメント