学校から連絡があって
○○さんが学校で友だちの物を壊してしまったんです・・・。
こんな電話を聞いたときはめちゃショックですよね
そんなときにどうすればいいの?
って思うと思います
何回もあることではないはず・・・なので、よりどうすればいいかより迷います
結論としては「まずは責任をとろう」です
ーーーーーそんな簡単に受け入れられませんよね…。
どんなふうにして責任をとるべきなのでしょうか
子どもとのトラブルも起こるのが学校ですので、どうやって責任をとることが子どもも大人もいい感じに終わるのか紹介します
はじめに
そもそもそんな電話があって一番初めに思うことは
1、状況を正確に把握しよう
まずは子どもや学校からの情報をしっかりと確認しましょう
何が起きたのか、いつ起こったのか、どのような経緯だったのかを子どもに優しく聞いてみてください
このときにあまり責めるような言い方をしてしまうと、ウソをついたり本当のことを話しづらくなります
『どうしてそんなことをしたの?』ではなく
『物が壊れる前にどんなことがあったの?』と状況を理解する質問をしましょう
学校と子どもの両方から話を聞く
学校から連絡があったときに、わかる範囲で自分のしりたいことを質問しましょう
大事なことは、「学校と被害にあった子どもの保護者の方にも状況を確認する」
です
完ぺきな話を共有できれば一番いいのですが、学校も保護者の方も子どもも人間ですので話に食い違いが生まれても不思議ではありませんよね
情報を学校・自分・相手の保護者で情報を共有することで解決策を見つけやすくなります
2、子どもと解決策を一緒に考える
子どもが相手に謝ることは大切ですが、それだけでは同じことを繰り返してしまう可能性があります
行動の背景を探る
『遊んでいてたまたま手があたってしまった』
『友だちとふざけていて、関係ない子のものを壊してしまった』
など状況はさまざまです
どんな場合であっても、どうしてそのような行動をしていたのかを一緒に考えてあげましょう
子どもの行動の背景を探ることで、子どもも自分の行動を振り返ることができます
「責任をとる」という姿勢を教える
壊してしまったものに対して責任をとる姿勢を学ぶのは、子どもにとっても大切な経験です
「ごめんなさいで済めば警察はいらない」
よく子どものときに聞いたフレーズですね
「ごめんなさい」の言葉だけでなくて、どうやったら相手が納得いってくれるのかを責任という言葉をつかって一緒に考えてあげましょう
すべて親が終わらせてしまっては、せっかくの経験をつぶしてしまうことになりかねません
出来事には頭を悩まされますが、子どもの成長だと割り切ってしまいましょう
3、被害者への対応
子どもに責任をとることを教えたいのであれば、まずは親が被害者に対して誠意ある対応を心がけましょう
すぐに謝罪する
まずは子どもと一緒に壊してしまった持ち主とその保護者に謝罪しましょう
このときにただ「すみませんでした」だけで終わるのではなく弁償も視野にいれた話をするのが大事です
連絡先がわからない場合は、学校に問い合わせて相手の保護者に連絡先を教えてもいいかどうかたずねてもらいましょう
わからずにうじうじしていると時間がもったいないです
弁償の相談をする
壊してしまったものが弁償可能なものであれば、電話や対面したときにその話を切り出しましょう
責任の取り方を子どもに見せるのであれば、同等品や代金で償うことが基本です
被害者の気持ちも尊重しながら進めていきましょう
4、学校との連携を大切に
学校で起きてしまった場合、学校との連携も必要不可欠です
子どもの話だけを聞くのではなく、学校の先生の話もきちんと聞くようにしましょう
担任の先生と話す
学校から提供される情報を参考に、再発防止に向けて相談するといいと思います
同じことが起こらないようにしたいのは学校側も同じですから、しっかり考えてくれるはずですよ
再発防止に向けた取り組み
子どもとのは話し合いも大事です
どうすれば同じことを繰り返さずに済むのか、学校のルールや決まりをもとに一緒に考えましょう
起こってしまったことだとしても、再発防止に努めることも責任をとることにつながってきます
5、子どもの心のケアも忘れずに
自分の行動によって友だちの物を壊してしまったという事実は子どもにとっても大きな負担です
それによって、自分だけでなく、先生や親、友だちの親にも迷惑をかけることになりますので、よりダメージが大きいです
叱りすぎない
「罪を憎んで人を憎まず」のように、人格を否定するような叱り方は控えましょう
子どもが反省している場合は、過度に叱ることはご法度です
過度に叱られることで自己否定感が強まってしまいます
反省していないとわかるようなときは、自分のしたことの重大さに気づくまで話を続けていきましょう
ポジティブな言葉かけも大事
「ダメだよ」ということがだけじゃなくて、『この失敗から学んだでしょ』といったポジティブな言葉をかけてあげましょう
まじめに考えてしまう子ほど、長く引きずってしまいますから
6、親自身も学ぶ姿勢をもつ
子どもの行動は親の行動を映し出していることもあります
この機会に、家庭での接し方や話し方、教育法などを見直してみるといいでしょう
家庭でのルールを確認
物を大切にする気持ちやほかの人への心配りについてふだんから話す機会をつくりましょう
家庭でできることは、学校や社会にでてからもできますので
親も学ぶ姿勢を見せる
これ、めっちゃ大事です
一緒に考えるから、一緒にがんばろうという姿勢を見せることで、子どもも安心することができます
それが子どもの安心感につながり前向きになれます
まとめ
子どもたちが物を壊してしまうのは誰にでも起こりえることです
この出来事を「悪いこと」だけで終わらせるのはもったいないです
子どもが責任を学び成長するきっかけとして捉えると親としての心もちにも余裕ができます
親としては一貫して冷静に、そして誠意をもって対応することが大事
そうすることで、子どもにも正しい価値観を伝えることができると思います
失敗から学ぶことの連続、そんなことは百も承知、一歩ずつ、子どもと一緒に成長しましょう!
以上でーす


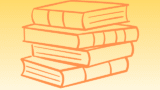

コメント