こんにちは!るうです!
子どもが生まれてから、幸せに包まれる一方で、多くの親が直面するのが「夜泣き」。夜中に突然泣き出し、なかなか泣き止まない赤ちゃんを前に、眠れぬ夜が続く……そんな経験をしている方は少なくありません。「どうして泣くの?」「何をしても泣き止まない……」と悩み、時には自分を責めてしまうこともあるでしょう。
今回は、そんなママ・パパの心が少しでも軽くなるように、夜泣きの原因と、家庭でできる対策について、わかりやすくまとめてみました。
夜泣きってなに?
まず、「夜泣き」とは、日中は特に問題なく過ごしている赤ちゃんが、夜間に突然泣き出し、なかなか泣き止まない現象を指します。多くの場合、生後6か月〜1歳半頃によく見られ、特に生後9か月前後にピークを迎えることが多いとされています。
夜泣きの時間帯や頻度には個人差があり、毎晩何回も起きる子もいれば、数日に一度という子も。泣いていても目をつぶったままの「半分寝ている」状態であることもあります。
夜泣きの主な原因とは?
夜泣きの原因は一つではありません。いくつかの要因が重なって起きていることが多いです。
睡眠サイクルの未熟さ
赤ちゃんは大人と違い、眠りが浅く、睡眠のサイクルも短いです。そのため、眠りが浅くなったときにうまく次の睡眠へ移行できず、泣き出してしまうことがあります。
日中の刺激
日中に新しい体験をしたり、刺激が多かった日は、その興奮が夜に影響し、夜泣きにつながることも。脳が情報を整理する過程で不安定になってしまうのです。 成長や発達の影響
はいはいを始めたり、立ち上がったりといった身体的・精神的な成長のタイミングでも、夜泣きが増える傾向があります。いわゆる「スリープ・リープ(睡眠の谷)」の時期にあたることも。
お腹がすいている/暑い・寒い
シンプルなことですが、空腹や暑さ・寒さといった環境要因も夜泣きの原因になります。大人でも不快な状態では眠れないのと同じです。
夜泣きをやわらげるための対策
すぐに夜泣きを「ゼロ」にするのは難しいかもしれません。でも、少しずつ頻度を減らしたり、赤ちゃんが安心して眠れる環境を整えることで、親子ともにぐっすり眠れる夜に近づくことができます。
寝る前のルーティンを整える
毎晩決まった時間にお風呂→ミルク→絵本→就寝、というように「寝るまでの流れ」を一定にすることで、赤ちゃんは「もうすぐ眠る時間なんだ」と自然にリズムを覚えていきます。特に絵本の読み聞かせや、やさしい音楽などは効果的です。
照明と音に気をつける
赤ちゃんの寝室は、暗すぎず、明るすぎない照明が理想。完全な真っ暗が苦手な赤ちゃんには、常夜灯や間接照明がおすすめ。また、テレビやスマホの音・光も眠りを妨げることがあるため、寝る前は静かな空間を意識しましょう。
お昼寝の時間を見直す
お昼寝をしすぎて夜に眠れないケースもあります。午後遅くのお昼寝は控えめにし、夕方以降はなるべく身体を動かして、適度に疲れさせておくとスムーズに寝入りやすくなります。
スキンシップを増やす
日中にしっかり抱っこしたり、語りかけたりすることで、赤ちゃんの「心の安心感」が高まります。夜泣きは不安や寂しさから来ている場合もあるので、スキンシップの時間を意識して作ってみましょう。
添い寝・添い乳の工夫
夜中に泣いたとき、添い寝や添い乳をするとすぐに落ち着く赤ちゃんも多いです。ただし、毎回同じ方法で寝かしつけていると「ないと寝られない」と思ってしまうこともあるので、少しずつ自分で眠る力も育てていけるようバランスが大切です。
親の心のケアも忘れずに
赤ちゃんの夜泣きは、親にとって心身ともに大きな負担になります。時には「なんで寝てくれないの?」「私の育て方が悪いの?」と感じてしまうこともあるかもしれません。でも、決してあなたが悪いわけではありません。
夜泣きは成長の一環であり、誰にでも起こりうること。完璧な対策や「魔法のように泣き止む方法」はないかもしれませんが、少しずつでも工夫を重ねることで、必ずゴールは見えてきます。
家族やパートナーと協力しながら、可能であれば時には祖父母や地域のサポートにも頼り、ママ・パパ自身がリラックスできる時間を意識して取り入れてみてください。
最後に:いつかは終わる、夜泣きの時期
今は大変かもしれません。でも、夜泣きは永遠に続くものではありません。成長とともに、少しずつ夜泣きはおさまり、ぐっすり眠る日がやってきます。
今はただ、その時期を親子で一緒に乗り越えるステップの途中。頑張りすぎず、たまには手を抜いて、どうか自分をいたわってください。
あなたと、あなたの赤ちゃんが、穏やかな夜を過ごせますように。


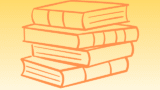
コメント