はじめに:学童保育と児童クラブ、何が違うの?
「学童保育と児童クラブって、どう違うの??」
こんなふうに思ったことはありませんか?
実はこの2つ、似ているようで違いがあるんです。
特に、
本記事では、学童保育と児童クラブの違いをわかりやすく解説し、
学童保育とは?
学童保育とは、正式には「放課後児童健全育成事業」
共働きやひとり親など、家庭で保育が困難な小学生を対象に、
自治体によってさはありますが、子どもを預かってくれるという点ではそこまで大きな違いはありません。
学童保育の概要はこんな感じです
- 対象:小学校1年〜6年(多くは3年生まで優先)
- 時間:放課後〜18時(延長ありの場合も)
- 料金:月額数千円〜1万円前後(地域差あり)
基本的には家で一人で置いておくのは危険と判断される小さい学年が対象ですが、場合によっては高学年まで利用できるパターンも数多くあります。
他にも、兄弟や姉妹で同じ学童を利用するという割合も高いです。
学童によっては、19時まで延長できる施設もありますが、ホームページなどで調べるか、実際に施設へお問い合わせいただくのが確実です。
児童クラブとは?
児童クラブは、自治体や施設によって「学童クラブ」「
実態としては学童保育と同じ目的・対象を持っていますが、
つまり、名前の違いだけでなく、
【比較表】学童保育と児童クラブの違い
| 項目 | 学童保育 | 児童クラブ |
|---|---|---|
| 管轄省庁 | 厚生労働省 | 自治体により異なる |
| 運営主体 | 公立・民間の委託など多様 | 主に自治体直営 |
| 対象年齢 | 小1~小6(多くは小3まで優先) | 自治体により異なる |
| 保育時間 | 放課後〜18時(延長あり) | 同様だが地域差あり |
| 利用条件 | 就労証明などの提出が必要 | 同様だが条件緩和の地域も |
| 費用 | 数千円〜(民間は高額な場合も) | 比較的安価なことが多い |
 ポイント:実際には地域によって「呼び方が違うだけ」
ポイント:実際には地域によって「呼び方が違うだけ」
例:東京都では「児童館」、大阪では「学童保育」
どちらを選べばいい?判断のポイント
「学童保育と児童クラブ、どっちを選べばいいの?」
これは、お住まいの地域やご家庭の事情によって異なりますが、
利用時間
延長保育があるかどうかは大きな判断基準になります。
学童によっても異なりますが、17時くらいまで子ども預かってもらい、子どもだけで歩いて下校するパターンと学童でお迎えを待つパターンがあります。
どちらを選ぶかに関しては、子どもが下校して家に着く時間に誰かが家にいるかどうかで判断するのがよいと思います。
歩いて帰る場合は、同じ地域の子ども達で集団になって下校します。
ただ、地域の人数によっては一人で下校する可能性もあるので注意は必要です。
何時まで預かってくれるのかは、学童によってさまざまなので、しっかり確認しておきましょう。
通いやすさ
学校や自宅からの距離は重要。
ほとんどの場合ですと、学校からそのまま学童保育に行くことが多いので、学校近辺の学童を利用することになります。
なので、下校するにしても送迎をするにしても学校までの登下校ができるのであれば、そこまで心配する必要はありません。
基本は、学校からの徒歩圏内に配置されていることが多いです。
民間の学童であれば、送迎のバスが利用できる場合もありますので、しっかりと確認しておきましょう。
保育内容
宿題のサポート、外遊びの時間、季節イベントの有無など、
学校から帰ってから学習をする時間が確保されていて、その時間で学校の宿題を進める場合もありますし、宿題のサポートを手厚くしている学童も中にはあります。
学校に隣接している学童であれば、学校のグラウンドを使って外遊びができることもありますし、学童によっては体育館を使用できる地域もあります。
基本的には施設の中で過ごす時間が長いので、ボードゲームやトランプをすることが多いのですが、遊ぶものがどれだけ充実しているのかも気にしておくといいかもしれません。
子どもの性格
人見知りや落ち着きのないタイプの子は、
とくに低学年のときは、学童に子どもを預けるご家庭がとても多いので、30人~40人近く、またはその倍くらいの子ども達が過ごすことになります。
見学や体験入所を通して、学童の雰囲気と子どもの相性を見極めることが必要になることもあります。
高学年になるにつれて子どもの数は減っていく傾向がありますので、その頃を見据えて一人で家で留守番をする練習をさせてみてもいいかもしれませんね。
保護者の働き方
フルタイム勤務や不規則な勤務時間の方は、
原則的な保育時間は各学童によって決まっていますが、延長保育があるかどうかはしっかり確認しておくことをおススメします。
多少料金はかかってきますが、仕事にも余裕をもって取り組みたいという方はとくに…。
ただし、学童は子どもを預かってくれる場所ではあるけれど、子どもがどう思っているのかは別物。
家でゆっくりしたいときもあると思いますので、子どもと相談をしてから決めていくと、お互いに納得のいく時間を過ごすことができると思います。
よくある質問(Q&A)
Q. 学童保育と児童クラブ、どちらも利用できるなら?
地域によっては、複数の選択肢から選べることがあります。
まずは見学に行き、施設の雰囲気や内容を比較しましょう。
Q. 高学年でも利用できる?
基本的には低学年優先ですが、自治体によっては小4〜
Q. 民間の学童保育とはどう違うの?
民間学童は保護者の就労要件がなくても利用できるケースも多く、
まとめ:自分たちに合った選択をしよう
学童保育と児童クラブは、制度上は似ていても、
最も大切なのは、「わが家に合っているかどうか」。
お住まいの自治体のホームページや学校、

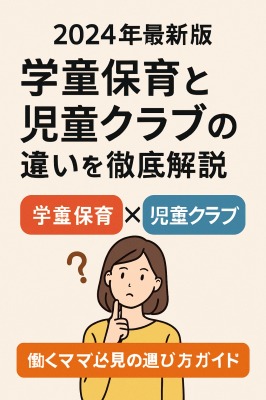
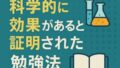

コメント