こんばんわ!るうです!
現代の子どもたちは、さまざまなストレスをかかえています。
スマホの普及による人との距離感の築きにくさや、それによる人間関係の不安など、学校や家庭でも、子どもの心に注目することが大切です。
子どもを理解し、子どもの心の声を聴けるようになるといいですね。
子どもの心のことを理解できると、その子にどんな声かけ、話し方が適しているのかもわかるようになります。子どもと関わる仕事をしていて、「子どもの心の声を聴くこと」は日々のコミュニケーションにおいてとても重要だと感じました。
子ども自身、感情を表に出す行動が一致するとは限りません。表情では笑っていても、心では悲しんでいる・さみしがっていることも十分考えられます。
すぐに子どもの心がわかるわけではないし、もしかしたら一生わかることができない可能性だってあります。
日々かわっていく子どもたちの心情を「わかろう」とする姿勢をもっておくようにしましょう。
子どもの心のSOSサインとは
子どもがSOSを出すときは、どんなときなのでしょうか。
それは、不安をかかえているときです。
心に不安をかかえていることで、表情や行動、体調が変化していきます。
例えば、急に態度が横暴になったり、物の扱いが乱雑になったり、です。
他にも、表情がいつもより暗くなり。腹痛や頭痛をよく訴えるようになったり、もします。
大人でもそうですが、表情や体調などを身ら柄、子どもと関わっていくようにしましょう。
子どものSOSサイン:チェックリスト
子どものSOSサインと思われる行動です。いくつチェックがあるか、ぜひやってみてください。
1,行動について
□笑顔が減ったり、表情がくらくなった。
□急にイライラしたり、怒りっぽくなった。
□落ち着きがなくなった。または逆に急に静かになった。
□趣味や遊びに興味を示さなくなった。
□食事の量が急に減ったり、増えたりした。
□夜に眠れない、または寝すぎるようになった。
2,学習について
□学校や塾に行きたがらない。不登校気味。
□宿題や勉強に集中できなくなった。
□成績や学習態度が急に悪化した。
□学校や友だちに関するネガティブな話をするようになった。
3,身体的なこと
□頭痛や腹痛をひんぱんに訴えるようになった。
□m気力な様子を見せることが増えた。
□爪を噛む、かみの毛を引っ張るなどのクセが目立つようになった。
いくつチェックがつきましたか?
あくまでも一例なのでこれが絶対というわけではないのですが、複数当てはまる場合は子どもの心理状態に何かしらの変化がある可能性が高いです。
そのまま話を聞くのではなく、それとなく子どもの様子を見守り、程よい距離感を保つことができるといいですね。
こういった傾向が見られる場合は、普段にも増して子どもの様子をよく見ておくようにしてあげてください。
子どもの心によりそうためのポイント
まずは、子どもの話をよく『聴く』ことです。
『よく聴く』というのは、いろんな可能性を考えながら聞いてあげるということです。
子どもが言ったことをすべて鵜呑みにするわけではありませんが、事実と自分の感情が混同してしまうこともあると知っておいて損はないと思います。
子どもが不安な気持ちになっていることがそのまま事実な可能性もありますし、嘘をついているわけではなく、子ども自身が気づいてなかったり、自分が感じたことを事実だと考えていることもあるので、注意が必要です。
だからこそ、よく話を「聴いて」どんな事実があったのかを聞けるといいと思います。
しっかり聞かずに早とちりをしてしまうと、子どもの信用を失ってしまうだけでなく、今後の関係にもひびが入ることになってしまいます。
いろんな視点から子どもを見守り、子どもの気持ちや話を深く聞けると、大人も子どもも安心して生活することができるので、試してみてください。


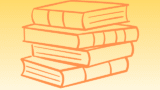
コメント