こんばんわ!るうです!
新学期が始まって、大人も子どももストレスがたまりやすい時期です。新しい人間関係をきずくことになり、それを強いストレスだと感じる人は多いはずです。特に、職場や部署がかわった人、新しい学年に上がった子どもたち、それぞれが新しい環境に胸をふくらませつつも、ストレスを感じていると思います。
今までの環境ですでに人間関係をきずけていたのならなおさらです。
「前はこうだったのに…」と思うことが強いストレスになるんですね。
そんなストレスを、今回は子ども視点で考えていき、そんなサインが子どもたちから発せられるかを考えていきましょう。
ストレスサインを見逃さないために知っておきたいこと
まずは、子どもの言動の変化に注目することです。
「どこかいつもと違うな…」と思ったら、よく見守ってあげるようにしてください。
子どもたちからは、どんなサインが発せられるのでしょうか。
二つ紹介します。
まず、一つ目は、心理的なサインです。
ストレス=不安に直結します。感情が不安定になったり、イライラしていたり、急に涙を流したり、さまざまな姿で出ることがあるのです。
二つ目は、身体的なサインです。
頭痛や腹痛、よく疲れるなど、ふだんの生活では見られない症状が体にでてくるようになります。
子どものストレスサイン ~こんな行動に注意~
では、もっと具体的にどんなストレスサインがあるのでしょうか。
注意すべき行動とは…
一つ目、口数が減ったり、会話が少なくなることです。
不安なことで頭が一派になり、話す余裕がなくなる人がほとんどだからです。
二つ目、学校や勉強に消極的になる。です。
新しい環境にまだ慣れることができていないので、一つひとつの行動が重いのです。
三つ目、食事や睡眠などの生活リズムの乱れです。
ご飯をあまり食べなくなったり、夜、眠ることができなくなったり、不安なことを考え続けていると、生活リズムにも影響を与えてくるのです。
ストレスサインを見つけたときは
いろいろなストレスサインをあげてきましたが、そんなストレスサインを見つけたときには、適切に対応して、不安を解消してあげるようにしましょう。
まずは、子どもの不安を聞きだすことです。何に不安をかかえているのかわからないままでは、こちら側も動けませんからね。
子ども自身も、何が不安なのか言語化できないことが多いので、ゆっくり聞き出してあげましょう。
このとき、まちがっても怒ってしまうのは、おススメおすすめしません。
怒らず、子どもが安心して話せる環境をつくってあげましょう。
学校の先生や親せきに協力してもらうことも必要です。
一人で何とかしたい気持ちはわかりますが、無理しようとせずに、周りの人にも助けてもらいましょう。
ストレスサインに敏感になるために
まずは、親や大人自身、時間に余裕を持つといいと思います。
どんな子どもの状態であっても、対応できるようにいておきしょう。そうすることで、相談しやすくなり、子どもの不安を打ち明けていいんだと、安心できるようにしましょう。


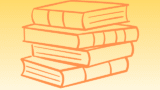
コメント