と感じることはありませんか?
『学級経営』と一口にいっても、一筋縄ではいかないのが現実です
では、どんな学級をつくっていけばいいのでしょうか
結論は、「ルールを守ったうえで自由に過ごせる学級です」
学級には子どもが約30人いるわけですから、決まりや規律がなければ無法地帯になってそれはもうすごいことになります…すごいことに(汗
かといって、規律を守らせようとしすぎると教室の中がギスギスしますし、ギスギスすると今度は子ども同士のケンカが多発するようになります
この場合のケンカは、仲がいいゆえに起こるものとはとは違って相手を陥れるものです
相手を陥れることで、自分が優位に立とうとするわけです
そんなケンカが起こるようになれば、いじめの前兆にもなりますので特に注意ですね
自分の気持ちをわかってほしいときに起こるケンカは、ふだんから関係がつくれているということなので温かく見守りましょう
かといってルールがあやふやで学級が安定していくことはありません
好き勝手な行動をとるようになるので授業が進めにくくなります
要は、『規律と自由のバランス』を見極めていくことが必要なんです
では、どうすれば学級が安定していくのでしょうか
この記事を読めば、どんなポイントで子どもたちを見ていけばいいのかがわかるようになりますよ
学級が安定するのコツ10選
さっそく、学級が安定する方法をご紹介していきます
- 最初の3日間
- ルールは少なく
- ほめる基準の明確化
- 『強み』を知る
- 役割をつくる
- 子どもに『任せる』
- トラブルは果実
- 感情は二の次
- 朝のスタートダッシュ
- 子どもの姿の見える化
それぞれについて解説します
1,最初の3日間
学校では、4月最初の3日間は『黄金の3日間』と呼ばれています

この3日間でこれからの一年間の7割が決まると言っても過言ではありません…と言われています
にわかには信じがたいですが、実際、影響はかなり大きいです
たった3日間がなぜそんなに影響力があるのかというと……
学級経営の土台になるからです
ルールや決まりごとは途中で変更することも可能ですが、何度もルールを変えてしまうと子どもたちも忘れたり混乱したりして安定しなくなります
4月初めの3日間は、ほんとによく話を聞いてくれるんです
子どもも新しい環境にわくわくドキドキしています
そんな思いもあってか、こちらの話を集中して聞いてくれることがほとんどなのです
そのタイミングだから、『黄金の3日間』と呼ばれているのです
どんな先生か、どんなクラスにしたいのか、どんな思いがあるのか、子どもに伝えたいこと守ってほしいことをきっちり伝えるのに効果的な3日間になります
それ以降にした話も聞いてくれますが、最初の3日間のほうが圧倒的に効果的なのは間違いありません
もし4月を逃してしまったときは、2学期や3学期の初めに話をするのも有効的なので覚えておいてくださいね
2、ルールは少なく

学校生活を送っていくときにルールは必ず必要です
日本という国でも決まりやルールがないと崩壊しますよね
それは学級でも同じです
ルールが少ないのがなぜ学級経営のコツなのか……
それは、『ルールが少ない=安定している』からです
ルールが多い学級では、子どもはしがらみだらけになるわけです
つまり、ストレスが多い。ストレスが多くて落ち着いた学級になるわけがない…ということです
ルールをなくすのではなくて、最低限のルールを守ることで安定するようにしていきます
減らして安定してくるということは、子ども達が育ってきていると判断する材料にもなりますよ
3、ほめる基準の明確化

何をすればほめられるのか、それを明確にしてあげましょう
ほめるというより『認められる』ですかね
良い行動と悪い行動が2:8だとすると、悪い行動を減らすのではなかなか改善しません
良い行動ができるように環境を整えていくことが大事です
ただ良い行動をして何もなければ、『良いことしてもなぁ…』という思いが募りますよね
大人ならそんなの関係なくやれよと思いますが、子どもとしては報われない思いを抱えたままになります
それを防ぐためにも、子どもが良い行動をして大人からも友だちからも認められる環境を整えていきましょう
まずは、そのクラスでは何が良いことなのかを明確に先生が決めてしまいましょう
それを日々子どもたちに伝えていくだけです
少しずつ、子どもたちの意識にも積み重なっていきますよ
4,強みを知る

子どもたちの『強み』です
何をするのが得意で、どんな行事や決め事に積極的に取り組んでいけるのか、それを見極めることが学級経営の大きな力になります
なぜ強みを知るのが大きな力になるのかというと…
子どもの力も学級の力として加えることができるからです
先生一人の力は大きいですが、子ども30人の力が合わさったほうが力が大きくなるのは言うまでもありません
子どもの力も加えて、より大きな力で学級を支えていきましょう
5,役割をつくる
子どもの強みを知っただけでは、学級の力として使うことはできません
子どもの大きな力を具現化するために、役割をつくるのです
力をうまく学級づくりに使うことができれば、学級の土台がとても安定してきます
子どもの力と大人の力をうまく合わせていきましょう
6,子どもに任せる

学級のあれこれって、すべて大人がやったほうが早くクオリティも高くなります
でもそんな動き方って長続きしませんよね
学校は一年を通して動いていきます
長い一年間を戦い抜くためには、先生一人の力では絶対に足りません
なので、子どもの力をたくさん借りていくことがおススメです
クラス全員に仕事を任せることができるのであれば、先生の負担は大きく減っていきます
子ども達をほめられる機会が多くなるので、お互いにメリットが大きいのです
7,トラブルは果実
学校では毎日のようにトラブルやケンカが起こってきます

しかしながら、そのトラブルがあるからこそ子どもたちと学級は成長していくのです
誰かと言い合ったり、殴り合ったり、でもその中には自分にも悪いところがあるけどそれを認めることはできない…そんな思いを子どもたちは抱えています
そんな心の負担を感じたあと、子どもたちの心は成長していくのです
筋トレのようなものです
壊れた筋肉が前よりも大きく強くなろうとするように、子どもたちの心も前よりも強く大きくなっていくのです
8,感情は二の次
学級を経営していくときに考えるのは、子どもの過ごす環境が適切であるかです
感情を出さないのは、学級経営の基盤である『子どもとの関係』を大事にしてほしいからです
子どもの行動にいちいち感情で反応していると、体の疲れも出てきますし、なによりすぐにのどが痛くなって体調を崩しやすくなります
さらに、感情的になっている人の心の底ってすぐにわかってしまいますよね
そうなってしまっては子どもに不安をあたえることになりますし、学級経営においてはなるべく控えておきたいところです
9,朝のスタートダッシュ
朝の時間はどんな仕事をするにおいてもゴールデンタイムです

子どもたちが登校してくるまでの時間、子どもたちが登校して1時間目が始まるまでの時間、朝は頭の中がすっきりしていて体力もあるので、この時間に宿題のチェックや今日一日の流れを確認しておきましょう
とくにおススメしたいのが、朝の時間に宿題のチェックを済ませておくことです
返し忘れも防ぐことができますし、毎日宿題を出している場合でも朝の時間にチェックする習慣をつけておくと安心して一日をスタートできます
10、子どもの姿を見える化する

どうやって子どもの姿が見えるようにするのか
学級通信や掲示板などで子どもの姿を紹介することです
がんばっている姿や取り組んでいることを写真として日々記録しておきましょう
その写真をみると子どもたち自身が自分の姿を客観的に見ることができますし、保護者にも子どもの姿を発信することで「こんなふうにクラスで過ごしているんだな」と安心感をもってもらえます
保護者の人たちの協力があるのとないのでは、学級経営のし易さに大きな差が生まれてくるでしょう
まとめ
いかがでしたか
学級経営にこれといった正解はありません
だからこそ、いろんな手立てを試してみて、上手くいかなければ違う手を考えていくだけです
学級経営は一朝一夕ではどうにもなりませんが、毎日のちょっとして工夫でどんどん変化していきます
子どもたちの力も借りながら、安心して毎日をおくれるような学級を目指していってくださいね
踏ん張っていきましょう
以上でーす


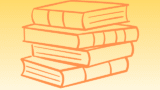
コメント