小学校の算数には、各学年ごとに山場となる単元があるといわれています
諸説ありますが(笑)
でも実際のところ、それぞれの学年での積み上げが算数科においてはとても重要です
1年生で習った内容は「2年生ならわかって当然」というていで進んでいきます
子どもの得意と苦手が大きくわかれるのも算数です
もちろん、どの単元も大事なことは言わずもがなです
どんな学習をしているの?
学年によって内容はちがいますが、学年を通して体系的に学んでいるので6年間の学習内容を知っておくと便利ですよ
ちなみに学年ごとの学習内容は
1年生:たし算・ひき算(くり上がりとくり下がり)
2年生:かけ算(九九の暗記)・たし算ひき算の筆算
3年生:分数や小数・かけ算の筆算・あまりのあるわり算
4年生:わり算の筆算・角度
5年生:分数のたし算ひき算(通分)・割合
6年生:速さ・比例・反比例
ざっとこんな感じです
ほかにも大切な学習はもちろんあるのですが、子どもたちはさきほどの学習内容でとくにつまずきやすいです
理由としては、
「1年生で習った基礎が2年生の学習ではできるものとして進んでいく」
のように、体系的に学ぶだからだと考えられます
1年生の学習が十分に定着していなければ、2年生の学習の学習でつまずくことは容易に想像できます
では、それぞれの学年ごとに具体的にみていきましょう
1年生:たし算・ひき算(くり上がり、くり下がり)
2年生:九九の暗記・たし算ひき算の筆算
2年生といえばかけ算の学習が出てくることはご存じかもしれません
九九を覚えているか覚えていないかで次の学年の算数につまずくかつまずかないかが決まるといっても過言ではありません
高学年になるとかけ算を使って学習する場面がめっちゃ多い
式はわかった
↓
九九を覚えていない
↓
計算に時間がめっちゃかかる
↓
算数イヤ
といった具合です
暗記には時間がかかりますし、覚えたと思っていてもすぐに忘れてしまうので、継続的に思い出すことが大切になってきます
おススメなのはyoutubeでもいいので、歌を使って覚えちゃいましょう
リズムで覚えられると、苦しさも少なく、かつ楽しく学習できますよ
3年生:分数と小数・かけ算の筆算・あまりのあるわり算
3年生になると整数だけでなく、小数以下の概念がでてきます
分数や小数は具体的な数で表すことが難しいので、理解するにも時間がかかります
おススメなのはケーキやピザを使って何等分にしたもので考えさせることです
具体的にイメージできると理解しやすくなります
小数はお金がいいですかね
かけ算の筆算やあまりのあるわり算もつまずきポイントですが、その話はまたの機会にしましょう
4年生:わり算の筆算
4年生の学習内容は「4年生の壁」ともいわれるようです
わり算の筆算は、今までの四則演算(たす、ひく、かける、わる)の計算がとても重要です
とくに割りきれない場合の計算でつまずきやすい傾向にあります
この計算に関しては、反復練習がもっとも有効だと個人的には思います
しかしながら、おかしなどを使って具体的に分配することでイメージすると理解しやすいです
角度に関しても難しいのですが、分度器の使い方をマスターしてしまえばすんなり理解できることが多いです
5年生:分数の計算・割合
3年生ででてきた分数の概念の応用で、分数や小数で計算する内容がでてきます
分数のたし算・ひき算はなかなか厄介でカバーする幅が広いです
まず、公倍数・公約数の理解ができていることが大前提としてあります
その二つの考え方を使って計算を組み立てないと
式はわかった
↓
計算に時間がかかる
↓
算数イヤ
になります。大げさですが、案外的を得ている気がします
割合もやっかいなのですが、これは反復練習で計算の型を覚えていくのがけっこう有効です
分数のたし算では、具体的に食材を使って表すことができますが、数が多くなったときにつまずきやすいので注意です
割合は、買い物で「20%オフ」「8割引き」という場面から考えると理解しやすいです
6年生:速さ、割合、比例
小学校6年間の学習の集大成ですね
6年生ですので、大人の介入を嫌がるかもしれませんが、困っているときに一緒に考えて上げれるといいと思います
山場となる速さの学習は、機械的に覚えてもいいかもしれません
速さの学習は、時速や分速など、感覚的に理解するのが難しい学習です
子どもに理解をさせたいときは、車で時速何キロかを実感させるのがおススメです
自転車でも走りでもなんでもかまいません
時間と速さの関係を体感してしまえば、理解が早まると思います
あとは、
子どものときにやった「は・じ・き」の法則をつかって機械的に教えるのも作戦的にはもちろんありですよ
比例と反比例はグラフにある2つの数値を読み取ることがひつようです
実際にグラフを用いて、比例反比例を可視化して教えていきましょう
まとめ
いかかでしたか
小学校6年間でも、子どもたちはたくさんの山場を乗り越えているのです
大きな壁を超えるにはそれなりに基礎が必要になってきますので、各学年で必要最低限の学習はおさえていけるといいですね
答えを教える必要はありませんので、教えるというよりは一緒に問題を解く
これが子どもとの関係を築くうえでも大切なことです
最終的にうまく教えられなくても大丈夫
子どもが困って、子ども自ら解きたいと思えることがとっても大事ですから
子どもと一緒に山場を越えていきましょう!
以上でーす

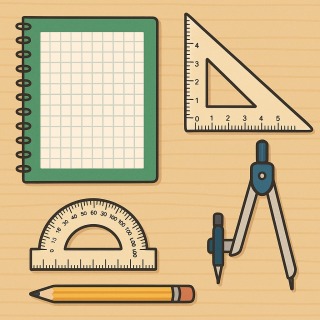


コメント