こんばんわ!るうです!
4月から新学期になり、新しい学年新しいクラスなど、新しい環境に身を置く子どもたちが増えたことでしょう。
新しい環境というのは、大人も子どもも不安なものです。
そんな不安な気持ちを親や大人たちはどうやって受け止めてあげたらいいのでしょうか。
この記事では、不安をかかえる子どもたちにどんな言葉をかけて、話を聞けばいいのか。ということを伝えていきます。子どもの不安を解消して、気持ちよく新しい環境に飛び込んでいってほしいですね。
なぜ、子どもの不安な気持ちを受け止められてますか?
新学期をむかえた子どもたちは、すでに不安をかかえ、明日のことを心配していることと思います。
「不安なことがあったら自分に言いに来るだろう」
『不安に思っていたら、何か子どもからサインや行動の変化があるだろう』
とか、そんな悠長なことを考えている場合ではないかもしれません。環境の変化は、子どもにとっても相当のストレスです。言われなくてもご存じだと思いますが・・・。
たとえ完ぺきでなくても、少しでも、子どもの不安を解消してあげるのが親であり、大人の役目なのだと思います。
不安な気持ちになっている子どもたちは、ふだんの力を十分に発揮することができません(それは大人もですが笑)
ということは、いち早く子どもの不安な気持ちに気づいて解消する道を探してあげることが必要です。
子どもの気持ちを引き出す魔法の言葉
どんな話し方であれば、子どもたちは不安な気持ちを打ち明けることができるのでしょうか。
まさかとは思いますが、
「何か不安なことある?」→『ないから大丈夫』
という会話をうのみにしないでくださいね。(そんなことはないとは思いますが。)
まずは、子どもがどんな生活を送ったのか、聞き出してみるのがいいと思います。
「クラスはどんな感じ?」
これだと少し押しが弱い気もしますね…。
たとえば
『クラスの担任の先生はどう?若め?ベテラン?』
などちょっとおやらけた感じでいきましょう!
正直、 しょっぱなからまじめな話をきり出されでも、話す気になれず「まぁ、ふつう」とか、そんな明確ではない答えが返ってくるでしょう。
いきなり突っ込まれた人は、答えもまとまっていないから、「ちょっとめんどくさい」んですよね。
「気になるそこ!?」くらいの反応が返ってきたら最高ですよね。
あとは、どんな子が同じクラスにいるの?とか、今日の学校で一番困ったエピソードやそれを「教えて?」という聞き方で聞いていきましょう。
そして少しづつ不安につながりそうな質問へとスライドしていっちゃいましょう。
会話のスタートで子どもの警戒心をほどいてから、心をほぐして本題に入るといいのです。
ちょったした情報の共有みたいなことができればバッチリなんですよね。
不安を言いやすくなる。聞く姿勢とは
ただイスに座って「大切な話があるから座りなさい」とか、ドラマのワンシーンみたいな聞き方をしてもドラマの通りにはなかなかいかないもんです。
子どもを心配する気持ちはもちろん大事ですが、「心配しているアピール」は心にそっとしまっておいてください。
それをやりすぎてしまうと・・・
「うっというしい」という言葉を聞く原因にもなってきますよ!
さて、聞く姿勢ですが、正直この姿勢なら絶対に話せる!なんて考えは甘いと思ってください。
子どもの考えや思考を100%知ることなんてできません。そう思うことが第一歩だと思います。
なにかと細かく質問攻めにして、ねほりはほり聞こうとしないようにしてくださいね。
では、どんな質問をすればいいのでしょうか。
それは「子どものほうが長く話すことができる」ように質問を吟味していきましょう。子どもがどんな質問や声かけだと嫌がるのか知っているのは間違いなく両親ですよね。相手が話しやすい話題を提供してあげることで、 コミュニケーションも気づきやすくなります。
まとめ
子どもの気持ちを受け止めることは、子どもの心の居場所を作ってあげることにもつながります。
そして、親や大人自身がドシっとかまえておきましょう。
子どもが不安を打ち明けたときに焦ったりうろたえたりすると、その不安が子どもにも伝わってしまいます。
仮に心で「え、大丈夫なの…」と思っていても、表情には出さず、「そうか、何か助けられることはあるかな?」と子どもが安心できる相手として存在しておきましょう。
とりあえず、親としては、オロオロしないで「どーん!」と山のように身構えて、子どもの話を聞いてあげましょう!


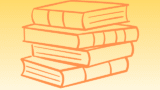
コメント